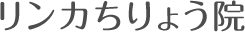不妊治療や妊活では、原因・年齢など異なること状態のことも多いですが、「お子さんがほしい」という思いは、どのご夫婦にとっても同じ思いであり願いです。不妊には、さまざまな要素が絡みあっています。要因や治療、鍼灸との関わりなどについてご紹介します。
目次
不妊治療
不妊の定義と保険の適用
健康なご夫婦が避妊せず、1年以上妊娠しない場合「不妊」状態にある。とされています。病院で治療を行うためには病名が必要です。不妊の定義は病院で治療を行うために便宜上病名が必要になるのでつけられていますが、病気ではありません。ただ、今は、不妊の状態にあるという状況になります。
2023年4月から不妊治療の体外受精や顕微授精などの生殖補助医療も保険の適応となりました。
年齢制限や回数制限などがあり、自由診療のときに行えていた検査や治療が行えなかったり、その他にも変更されたことがあるようです。保険の適応にはメリットもデメリットもありますが、でも、一番大切なのは、保険の適応開始前と開始後での妊娠率の変化です。まだ、始まったばかりなのでこれから問題点も出てくる可能性は高いですが、妊娠率または出生数が上がることを願っています。
不妊と関係の深い因子
不妊治療のため病院受診をすると血中のホルモン数値や卵管や子宮などの検査します。それらの検査で分かるのは、不妊と関係の深い因子です。不妊治療が進んでいくと、基本的な不妊因子の検査内容だけでなく、子宮フローラ検査や子宮の窓などの詳しい検査を行いますが、ここでは、基本的な不妊治療開始時の不妊因子についてになります。
不妊因子には
① 内分泌・排卵因子
② 卵管因子
③ 子宮因子
④ 頸管因子
⑤ 免疫因子
⑥ 機能性不妊(原因不明)
などがあります。
検査により明確な因子が発見された場合は、その治療を行うことで不妊因子はなくなります。ただ、検査により因子が見つからなかった機能性不妊(原因不明)、また、発見された因子は取り除けたのに妊娠に繋がらない場合などは、その原因因子を特定することは難しくなり、不妊因子がないのではなく、見つからなかったという考え方もできます。

不妊因子
不妊因子にはさまざまあります。
内分泌・排卵因子、卵管因子、子宮因子、頸管因子、免疫因子についての原因や検査などをご紹介しています。
不妊と免疫細胞
不妊と関係の深い免疫細胞は複数あり複雑です。しかし、妊娠を持続させるにはお母さんの免疫学的寛容(トレランス)と関わりのある免疫細胞はとても重要になります。
母体の免疫学的寛容(トレランス)とは
不妊と母体の免疫学的寛容は切り離して考えることはできません。
人の身体の仕組みには、自分の細胞と異なるものを排除するシステムが備わっています。受精卵や胎児の細胞には精子由来の細胞が含まれているので、排除しようと免疫細胞が働くと着床不全や流産などが起こります。
着床した胚の周囲には多くの母体リンパ球が集まっていることが知られていました。これは、胎児がお母さんに認識され受け入れられていることになります。胎児は、お父さんとお母さんの細胞を受け継いでいるのでお母さんとは異なる細胞になります。ですから、そのまま免疫細胞が働くとお母さんから拒絶される可能性もあります。胎児がお母さんから拒絶されないのは、妊娠時にお母さんの体内で免疫学的寛容(トレランス)が働くからです。このトレランスを獲得することにより、胎児は子宮内で成長し、出生後は母乳で育つことができます。マウスの研究では妊娠期間中に限って父親抗原特異的トレランスが存在することが分かっています。その証として、母親のリンパ球の父親リンパ球に対する反応性の低下や脱落膜中での細胞傷害性T細胞の減少が報告されています。
不妊と関連のある免疫細胞
免疫に関連する細胞は、サイトカインも含めさまざま存在し、複雑に絡み合って免疫学的寛容(トレランス)の仕組みが動きだすようになっています。今は、まだ、分かっていない細胞も存在するかもしれませんが、現段階で、不妊と関連すると報告されている免疫細胞は下記の通りです。
① NK細胞
② サイトカイン
③ Th1/Th2バランス
④ 免疫グロブリン
⑤ 制御性T細胞細胞 etc…

不妊と免疫細胞
免疫細胞は怪我や風邪などのウイルス感染などだけでなく、不妊や妊娠の維持と大きな関わりがあります。免疫細胞の働きについては難しくもありますが、知っていると役立つことがあるかも?
不妊とストレス
ストレスと不妊の関係は深いと考えられています。不妊治療や妊活にストレスがどのような影響を及ぼす可能性があるのか?ご紹介いたします。
ストレスって言葉よく耳にします。まず、ストレスって何?と思いませんか?ストレス理論では、人生の中で様々な出来事(ストレッサー)に遭遇するが、その遭遇した出来事が自分の対処能力を超えた脅威であると感じる時に、ストレス反応と呼ばれる症状や行動を生じさせます。とあり、ストレスとは、症状の原因となるストレッサーのことと考えられます。
ストレッサーには強さがあり、強いストレッサーは大きなストレス反応を引き起こします。文部科学省のサイトでは、ストレッサーの種類を次の3つに大別しています。
① 生活環境ストレッサー
② 外傷性ストレッサー
③ 心理的ストレッサー
どのステレッサーも取り除く、もしくは緩和できることが大切ですが、妊活で大切なのは
ストレス反応は、生活環境ストレッサー、外傷性ストレッサー、心理的ストレッサーが全て加算され、複合的に作用し引き起こします。ですから、どの種類のストレッサーも取り除く、もしくは緩和できることが大切です。ただ、不妊治療をしていると「~するかもしれない」「~したらどうしよう」と考えることが多くなる場合があります。これらの否定的な予期や評価という思考自体が心理的ストレッサーとなり、不安や恐怖、緊張といったストレス反応を引き起こし、ストレス反応が継続することになります。
ストレッサーの影響を受けやすいところ
呼吸、循環、栄養、体温、生殖などを常時調節し、生体のホメオスターシス(恒常性)の維持に重要な働きをしている自律神経とストレス緩和ホルモン(副腎コルチゾール)が分泌される副腎皮質ホルモン分泌反応です。
ストレス反応で起こること
ストレスは、日常生活の中で切り離すことはできないものです。そして、ストレスは不妊治療をされているご夫婦にとって大敵だと考えています。どんな影響があるのかを知って、上手に付き合う方法を探していただいきたいです。
① 女性ホルモン分泌の乱れ
② 免疫力低下によるカンジタ膣炎などの罹患
③ プロラクチンの上昇
④ 卵子の効果促進
⑤ 卵巣や子宮の機能低下 など

不妊とストレス
ストレスは、さまざまな症状と関係があります。ストレスとよく耳にしますが、ストレスについて考えてみませんか?また、不妊治療や妊活でもストレスは大敵です。ストレスによりどのような変化が起こるのでしょうか?
医療機関で行う治療の種類
不妊治療は、タイミング法から段階を踏んでステップアップしていきます。治療方法は、タイミング法、排卵誘発法、人工授精、体外受精などがありますが、それぞれについて簡単に説明していきます。
1.タイミング法
不妊治療第一段階
経腟超音波検査で卵巣内の卵子が入っている卵胞の大きさを測定し、さらには、医療機関によっては排卵検査薬で検査を行い、排卵日を予測してタイミングを合わせる方法です。
2.排卵誘発剤などの種類
・ クロミフェン
・ ゴナドトロピン製剤(hMG製剤、精製FSH、遺伝子組換型FSH製剤 etc)
・ レトロゾール(不妊治療薬として、2022年4月に承認)
タイミング療法の段階で、ホルモン値に異常がなくても排卵誘発剤の服用をすすめられることがあります。排卵誘発剤は、排卵の時期を計画的に予測でき、妊娠率がUPすることが期待できます。
排卵誘発剤について詳しくはお知りになりたい方は一般社団法人 日本生殖医療学会をご覧ください。
排卵誘発剤には副作用があるものもあります。副作用については、あまり詳しく書かれていないかもしれませんが、少しは書かれていたと思います。
3.人工授精
不妊治療第二段階
ヒューナー検査や精子に問題がある場合などに行われたり、タイミング法で妊娠されなかったご夫婦にステップアップとして行われたりする治療法です。
精液を遠心機などに入れて精子を洗浄・回収します。その精子を排卵の時期にチューブ使って子宮内に注入する方法です。
4.生殖補助医療
不妊治療第三段階
生殖補助医療には体外受精と顕微授精があります。どちらも腟から卵巣に針を刺して卵子を取り出し、体外で精子と受精させ、新鮮胚もしくは凍結胚などの受精卵を、後日、子宮内に移植する方法です。
顕微授精は、卵子に直接、精子をひとつ入れて受精させる方法です。
生殖補助医療には、リスクがあります。
お子さんを望まれるご夫婦の方々には、リスクの可能性も承知して、ご夫婦でしっかり話し合って生殖補助医療について考えていただきたいです。症例は少ないかもしれませんし、今後、各医療機関の努力によって更に減少していくと期待していますが、リスクについて知っていたか?知らなかったか?この違いは大きいです。
参照
医療機関で行う不妊治療が保険の適応となりましたのでガイドラインに沿ってどこの医療機関も進められると思います。自由診療のときは医療機関によって検査の種類や治療方法が大きく異なることもありましたが、その可能性は少ないです。一般的な治療法などについてお知りになりたい方は、一般社団法人 日本生殖医療学会をご覧ください。さまざまな質問に対して、回答がしてあります。

参考 公益社団法人 日本産婦人科学会 妊娠維持機構/流産に関連するトピックス
AASJ 母親のNK細胞が胎児の成長を助ける(12月19日号Immuuity掲載論文)
Science Signaling 末梢血NK細胞のTim-3シグナル伝達が母体胎児間の免疫寛容を促進し流産を抑制する
Medical Tribune(2007年2月8日)、メディカルパーク横浜 培養室ブログ など
妊活鍼灸
妊活には、日常生活に運動を取り入れたり、サプリメントで不足している栄養素を取り入れたりとさまざまありますが、その中に鍼灸治療を取り入れていただくことです。妊活に鍼灸治療を取り入れていただくことで今までに感じたことのない効果が期待できる場合があります。
妊活鍼灸の目的と期待できること
お身体全体としての目的は、妊娠しやすいお身体の体質改善です。
妊活では、女性ホルモンの分泌や卵子の質の向上、子宮内膜の状態なども気になるところです。鍼灸治療は、何千年も前から先人の鍼灸師さん達が経験し、伝承されてきた治療法です。その中には婦人科疾患の治療や妊活に有効だとされる経穴があります。また、最近の研究により妊活に有効だと報告されている経穴などがあります。それらの治療穴を選んで治療を行うこと、骨盤内腔の血流増加を目的として治療を行うことで卵子の質の向上や子宮内膜をよりよい状態に保つお手伝いを目的としています。

鍼灸治療は、鍼をした際、リラックス時に観測される脳波が観測されることが研究により報告されています。手足に鍼をすることでリラクゼーション効果が得られると考えられています。このリラクゼーション効果により以下のさまざまな効果が期待できます。
・ 卵子の質の向上(受精卵のグレードUP)
・ 卵子の老化防止
・ 女性ホルモン分泌の正常化
・ 子宮内膜状態の改善
・ 免疫力UP
・ 骨盤内空の血流量増加
・ ミトコンドリアの増殖促進 etc…
不妊と低反応レベルレーザー治療
不妊治療や妊活のために鍼灸治療に来られた皆さんの治療には、必ず、鍼灸治療とスーパーライザー照射を併用して治療を行っています。当院では、どちらもかかせない治療です。
『不妊診療のための卵子学』の中に不妊に対する低反応レベルレーザー(以後、LLLTと称する)照射について成果をあげていることが紹介されています。
その中から、内容を少し抜粋してご紹介させていただきます。
週に1~2回、治療回数10回を境にして明らかな妊娠率の増加が認められた。
1996年~2009年までの間に行ったLLLT照射により、難治性不妊の方全年齢群において約20%の妊娠率を得ていると報告されています。
スーパーライザーの効果
スーパーライザー照射作用により期待できる効果はさまざまあります。
血流増加のよる効果
・ 視床下部への血流量増加
・ 子宮や卵巣の血流の改善
・ ミトコンドリアの増加(ATP合成増加)
・ 組織や細胞などでの浮腫やうっ血の改善(老廃物除去など) etc...
自律神経調整による効果
・ 免疫機能の制御
・ NK細胞の異常の緩和(NK細胞で着床不全の原因となる細胞の低下)
・ アレルギー反応の緩和
・ 消炎鎮痛作用(抗炎症性サイトカインの増加)
その他
参考 光線療法治療機
低出力レーザーの生体作用
低出力レーザー照射療法 etc

不妊とスーパーライザー
スーパーラーザーを照射すると妊活としてどのような効果が期待できるのか?ご紹介しています。
妊活鍼灸でこころがけていること
妊娠していただき、不妊治療と鍼灸治療を卒業していだたけるのが一番です。そこを目標にしています。ですが、治療を続けてもなかなか結果に繋がらないご夫婦もいらっしゃいます。鍼灸治療をして妊娠・出産されることに繋がることを一番にこころがけていますが、これが全てではない!とも思っています。
不妊治療や妊活をされることによって、さまざまな経験をされます。辛い経験もあると思います。でも、不妊治療をすすめながら経験する辛いことも嬉しいこともどのように捉え、時間を過ごしていくか?ということも大切なことだと考えています。不妊治療中に経験した辛いことも嬉しいこともどう捉えるかによって、不妊治療がどのような結果になってもあなたの心が苦しむことなくあり続けてほしい!と願って、皆さんとお話しをすること。きちんと向き合っていくことを心がけています。
お気軽にお問い合わせください0986-36-7121受付時間 10:00-19:00[月・木除く]
お問い合わせ